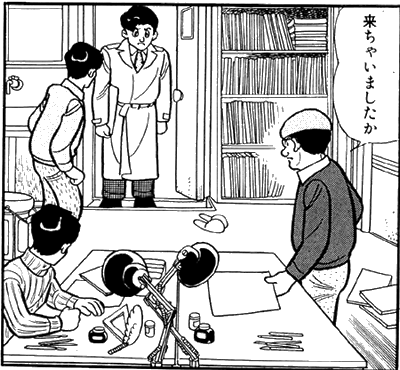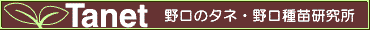
「手塚治虫先生の夢を見た話」
−手塚先生と僕のことなど−
以下は、まぎれもなく、眠って見ていた夢の話です。ただそれだけですので、あまり深くお考えになりませぬように。
今でも、一年に一回ぐらい、手塚先生の夢を見ます。
今朝方見た夢は、こんな内容でした。
十数人の男女と、どこかの山道にいた。僕は自転車を乗り捨て、続く人々も、それぞれ自転車や自動車を道ばたに停めて、僕の後に続く。僕は、なにやら白い紙に載せた物を両手で持ち、こぼれないように腰だめで持ちながら、道を外れて、草が生えている坂を下る。人々が後に続く。どうやら、手塚治虫の新しい記念館か、誰も知らない記念の建物に、みんなを案内しているようだ。
案内しているのだから、僕はその場所を知っているのだろう。坂を下りきると、下の道に出る。下の道は、上の山道と違い、平坦である。この道を右に行けばいいのだが、以前来た時と違い、道の手前にぬかるみがある。ぬかるみを渡らないと道に上がれないので、どうしようかと思いながらくるぶしあたりまであるぬかるみの中に入って行くと、何人かが後に続く気配だ。安心して道に出て、右に進む。
なにやら立派そうな建物の前に来るが、薄暗くて人の気配も無い。「ここじゃないんだよ」と、無言で後ろに示し、さらに道を進むと、粗末な木造家屋に突き当たる。
勝手口らしい古ぼけた木の扉をがらり開けると、そこに手塚先生がこっちを向いて立っていた。
「来ちゃいましたか」
その声は、困ったような、喜んでいるような、不思議な懐かしい響きだった。
―――――ここより思い出―――――
昔、そっくり同じ言葉を聞いたことがある。
虫プロ出版部が出していた月刊漫画専門誌『COM』の創刊当時、初の国産テレビアニメ『鉄腕アトム』の人気にかげりが出て、ついに放映終了が決まり、代わる『悟空の大冒険』と『ジャングル大帝』、それに『リボンの騎士』の三本が製作中で、スタジオも第一(アトム→悟空)、第二(ジャングル)第三(ワンダースリー→わんぱく探偵団だったカナ?)から第四(リボン)、第五(新規企画室)と五つに増え、総社員数500人と、過去最大規模になっていた。それだけに資金繰りも厳しいようで、重役が仕事中の先生に緊急面会を申し込み、仕事中の手塚治虫社長を手塚邸二階の応接間に連れ出して、何やら深刻な相談をしているらしいのが、傍目にもうすうす感じられた。金の話が嫌で、できれば漫画だけ描いていたい手塚先生は、ついに「雑用が多くてここでは仕事ができません」と、富士見台の自宅から、仕事場を中村橋の本屋の二階のアパートの一室に移し、漫画部(虫プロのアシスタント十人ほどの部署)全員引き連れて出て行ってしまった。がらんとした自宅の仕事部屋で、原稿が上がったと言う連絡を待つだけになった我々手塚番編集者は、なすこともなくソファーでだべったり、本を読んで時間をつぶすだけの日々だったが、どこも編集長や印刷所からの催促はきつく、誰も口に出せないイライラを抱えていた。スケジュール上は、ちょうど、僕が担当する『火の鳥』の順番の時のことだった。
「これまでの郵送ファンクラブ雑誌『鉄腕アトムクラブ』と違い、『COM』は書店販売の普通の雑誌です。今後は社内原稿だからと言って順番を譲れません」と大見得切っている手前、順番が来ているのに原稿が上がって来る様子がないからといって、他誌の編集者に相談するわけにもいかない。(みんな僕のお手並み拝見という態度)朝から何度中村橋に電話してもお話中で、やっと通じたのが夕方だった。
「虫プロ漫画部です」
チーフの鈴木勝利さんが出た。
「出版部の野口ですが。先生ちゃんと仕事してらっしゃいますか?」
「ええ、朝からお宅の原稿をやってますよ。どうしてですか」
「いえ、朝から電話してもずーっとお話中だったものですから」
その時、脇から
「なんですか」
と、手塚先生の不機嫌そうな声が聞こえた。
「野口さんが、先生は仕事しないで電話してたんじゃないかって」
うわ。しまった。と、思う間もなく、
「貸してください」
と、先生が電話を取った。
それからの先生のお叱りの言葉の数々を、とても文字に現すことはできない。僕は、ただ「はい」「はい」と、聞いているだけだった。
数分後、ガチャンと受話器を置く音が轟いた後も、受話器を握ったまま立ちつくしていた。
「はい。わかりました。じゃ、よろしくお願いいたします」
と、相手のいない電話に言った後、編集者用の電話を、力無くソファーの前のテーブルに置いた。
「どうだった?」
ソファーに座った『少年』の辻川理氏が、読んでいた雑誌を膝に置き、心配そうに声をかける。
「どうもこうもないよ。だめだね。何もやってない」
そして気を取り直して言った。
「どうせ今日は仕事にならない。明日は必ず上げてみせるから、今夜は憂さ晴らしに僕がおごるからみんなで飲みに行こう。先に出て待ってるよ」
編集者の控え室兼寝室である車庫脇の六畳間に戻り、コートを羽織って玄関から外に出た途端、どっと涙が溢れ出た。
その晩、一人で手塚邸の六畳間に寝た僕は、翌朝中村橋のアパートに向った。編集仲間には昨夜、「明日は仕事場に乗り込む」と、宣言していた。
「もし来たら、以後その雑誌の仕事はしない。と、言われているのに、大丈夫か?」
と、心配する声が多かったが、
「これ以上遅くなったら、みんなに迷惑がかかる。任せておいてくれ」と、また大見得を切った。
アパートの部屋をノックすると、下村風介が開けて、驚いた顔をしている。
「先生。来ちゃいました」下ちゃんの肩ごしに、奥に向かって声をかけた。
部屋の奥で先生が、机に座ったまま振り向いて、おっしゃった。
「来ちゃいましたか」
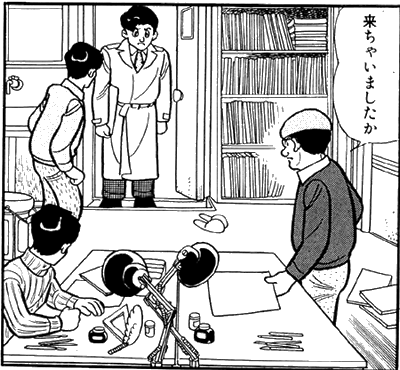
↑手塚プロ/伴俊男作画「手塚治虫物語」(朝日新聞社/1992刊)の中の僕
―――――ここで思い出はいったん終了し、夢の続きに戻る―――――
忘れられないあの時と、同じ言葉だ。違ったのは、あの時続いた言葉は、
「しょうがない。今からかかりますから、そこに座って待っていてください」
だったが、夢の中の手塚先生は、
「何人ですか?」
と、聞いたことだ。
僕はちょっと振り返って、
「十人ぐらいです」
と、答えた。
「まあ、入ってください」
先生が、自ら僕らを部屋の中に招き入れた。
中は古ぼけた畳敷きで、スチールの事務机が所狭しと並んでいたあの時のアパートの仕事部屋と違って、座机がぽつんと一つ置かれており、それを囲むように五人の若者が車座になってあぐらを組んでいる。
「元『COM』編集者の野口○んです」(「くん」と言ったか「さん」と言ったか覚えていない)
二十歳前後の若者たちが、いっせいに頭を下げた。
一人が言った。
「先生に会いたいと手紙を出したら、手塚プロのチーフから、ここに来るように指示されたんです」
へええ。今のチーフだったら福元一義さんだろう。事務的な印象なのに、粋なはからいをする。と、感心していると、
「同じく『COM』編集部の○○です」
「私は一読者の××です」と、僕に続いて入って来た人々が、勝手に自己紹介を始めてその場が混乱し、収拾がつかなくなった。
混乱に巻き込まれながら、僕は、今日こそあることを言ってしまおうかと、じっと考えていた。
先生が机に戻ったのを確認して、僕は意を決して横に座り、這いつくばるように土下座をして、言った。
「お願いです。サインしてください」
手塚先生がこちらを振り向こうとした。
と、ここでいきなり目が覚めました。(苦笑)
目が覚めた後、寝床の中で、僕はしばらく満足感に浸っていました。
「やっと言えた」と。
今まで、何度先生の夢を見ても、言えなかった一言でした。手塚先生を捜しまわって尋ね歩き、やっと会えても、原稿待ちの催促顔しか見せられず、夢から覚める度に、「ああ。一言言えば良かった」と、残念でたまらなかった一言でした。
「これでやっと、手塚番から、手塚ファンに戻れた」
そんなほっとした気持ちに、寝床の中の全身が、包まれていました。
小学生時代からの手塚治虫ファンで、手塚治虫先生のそばにいたい一心で大学を中退し、虫プロ出版部に入社したのに、いざ漫画の神様の伴走者の立場になってみると、「サインしてくれ」という言葉は、立場上絶対言ってはいけない一言でした。
「野口さんが結婚する時は、ボクが仲人をしてやるからね」
と、手塚先生がおっしゃったことがありました。それは僕にとって、「その時だけは堂々と、記念の色紙を描いていただける時」でしかありませんでした。
(そんなチャンスも、後に虫プロの仕事を放り出して、岡田史子と駆け落ちするという事件を引き起こしたため自ら投げ出してしまい、仲人は永島慎二先生ご夫妻にお願いするしかなかったわけですが)
僕の精神構造の大部分は、幼い頃から読み続けてきた手塚漫画で成り立っています。手塚治虫という存在は、僕にとって、実の父以上に父親的な、血肉を分けていただいたような存在でした。
それが、いざ本人と至近距離で接した時から、手塚治虫の仕事がスムーズに運ぶようにお手伝いしたい。邪魔にだけはなりたくない。そして絶対嫌われたくない。という、憧れが先に立つ編集者としての役割が、全てに優先するようになりました。目の前で仕上がっていく漫画を読んでも、「ああこれで今月も無事終えた」という気持ちが先行し、感動することが少なくなりました。作品の偉大さに比較して、生身の手塚治虫の子供っぽさや、たまに起す周囲の人間への癇癪に、卑小観を感じたことさえありました。
そんな時に起ったのが、前述の思い出話で触れた、我が身にふりかかった叱責(というか、これでもかと言わんばかりの罵詈雑言の嵐)事件でした。それまでの二年間、仕事場に二人だけの時など、
「野口さん、虫プロで一番いい人と見合いさせて欲しいという娘さんのご両親が来たんだけれど、お見合いしてみませんか」
と、言われたことがあったりして、先生に買われ、可愛がられているという秘かな自負があっただけに、その落差によるショックの大きさは、例えようもないほど大きかったのです。
また、僕が「編集者は絶対来てはいけない」という禁を破ったため、以後はどの編集者も平気で中村橋のアパートに行くようになり、先生にとってせっかくの安息所が、執筆だけに専念して安らげる場所ではなくなったことも、(アシスタントが多くいる以上、早晩そのようになることはわかっていたにしても)僕がとるべき行動でなかったのも、反省しなくてはいけない大事件でした。
(とはいえ、あの時手塚治虫先生が『火の鳥』を描いたスピードは、それまでもそれ以後も、一度も見たことが無いほどの、驚異的な早さでした。朝10時頃から取りかかった原稿24ページが、午後にはほとんど先生の手を離れ、畳に仰向けに横になった先生に、「これでどうですか」とアシスタントが原稿用紙を差し出すと、「はい」と横に置かれた眼鏡をかけて見つめ、「ここにこれを描き足して」とか「はいこのページはマルです」と言って、欄外に完成の印の赤丸を色鉛筆で入れさせたりして、猛スピードで仕上がっていきます。最後まで残っていた最終ページの大ゴマ、鈴木勝利チーフ担当の夜の海の大船団のバックのベタ塗りまで終り、「先生どうでしょうか」と僕が見せると、「はいマルです。これで完成です」と、おっしゃった時は、冬の最も日が短い時期だというのに、まだ日が沈んでいませんでした。マルを付けて受け取った原稿の数を数えて虫マークの封筒に入れ、横になったまま目を瞑っている先生のそばに膝まずき、「先生、ありがとうございました」と言ったとたん、先生はガバッとはね起きて僕の前に膝まずき、畳に両手を付いて、「こちらこそ、ありがとうございました!」と、22才の若造に、深々とお辞儀したのでした)
先生が真意を現そうとしたその態度を眼前にした僕は、本来その瞬間から前日の非道な発言を許し、改めて先生に感動して、それまでにも増して手塚治虫という人を尊敬するべきでした。その日、原稿をいただいて改めてお礼を言い、ドアを閉めて廊下に出た僕は、まだ人間ができていないため、そうではありませんでした。
朝、アパートに向かう時の、一か八かの高揚感が残っていたためかどうか、つい、「勝った(もちろん昨日の手塚先生にです)」と、思ったのでした。今度手塚先生にお会いした時、いつまた同じような目に会うかしれない。その時は、動揺しないで対応できるようにしよう。そうでないと、僕は、自分が理想とする漫画編集者でなくなってしまう。という思いから、以後、手塚先生に対し、予め構えて接するようになってしまいました。
一ヵ月ほど後、「もう何も怖くなくなった」僕が、未来の漫画の芽として評価した漫画をめぐり、今度は山崎邦保編集長に叱責されました。「俺は評価しない。今回だけは時間が無いので紙面に載せるのを黙認するが、以後は俺の言う通りにしろ」と言われ、すぐさま辞表を出したのも、だから僕にとっては、きわめて自然な流れでした。「奴隷より死を」と、言ったら、言い過ぎでしょうが。
(後で聞いた話では、この時僕が取り上げた岡田史子のわずか2ページが、ほかのどの漫画よりも読者に支持されたとかで、この女子高生は、以後『COM』の人気作家になっていきます)
入社して始めて知った川越高校の先輩、元光文社『少年』の『鉄腕アトム』担当、桑田裕出版部長に、「山崎君と野口君のどちらかを選ばなければならないとしたら、今は山崎君を選ばざるを得ないから、辞表を受理する」と言われ、「組織ですから当然です」と答えて、最初の虫プロ社員としての生活を、わずか二年間で幕を降ろしました。なぜかこの時は、手塚先生にご挨拶に伺わず、失礼してしまいました。たぶん、気持ちの小さい僕には、まだ、手塚先生に謝罪することができなかったのでしょう。
実家のタネ屋に戻ってわずか一週簡後、突然『少年』の辻川氏が、上司の細木さんを伴って、うちに現れました。光文社で、桑田部長と同期というふれこみの細木さんいわく、
「光文社で、新たに『手塚治虫漫画選集』を出すことになりました。ついては、それを君に編集していただきたい。これは、手塚先生の希望と思ってもらってけっこうです。給料は、本来君と同じ年の人間である、今年の光文社の大卒初任給(3万8千円という話でした)より多い、4万円を払います。ただし、正社員ではなく、この企画だけ担当の契約社員です。それでもよろしかったら、ぜひ引き受けていただきたい」また、
「せっかく家に戻ってくれて、喜んでいるであろうお父上には、また漫画の道に引き連り込んだのでは、迷惑に思われるかもしれない。そこで、なんとかお父上のご了解をいただくために、今日はこうして参上しました」と、初対面の僕に向かって、ていねいに言われたのでした。
こうして、漫画編集者としての第二の人生を歩み始めたのですが、残念ながらこの企画は、わずか半年後の1968年暮、『週刊新潮』に、「虫プロ倒産の危機」という記事が掲載されたことがきっかけで、カッパブックスのヒットメーカー、光文社神吉晴夫ワンマン社長の鶴の一声により、「時期尚早だ。企画延期。編集部解散」という憂き目を見ることになってしまいました。
編集部と言っても、僕一人しかいないのですから、要は、僕が首を切られただけでした。見本刷りまで出来上がり、もうすぐやってくるクリスマスには、三大紙に全面広告を打つ予定でした。一冊1000円という、当時としては豪華本の『手塚治虫漫画選集』は、こうしてクリスマスの創刊直前に幻となって終りました。
寝泊まりしていた光文社別館の編集室を片付け、手塚先生に、「表紙の絵はどんなタッチがいいですか?」と聞かれ、「できれば『おもしろブック』時代の、『銀河少年』のようなタッチの絵が欲しい」と言ったところ、「そりゃ無理です。今のアシスタントじゃ、あの色塗りはできません。表紙の感じでは?」と再度尋ねられ、「バックにはできれば白を生かしたものを」という希望を聞き入れていただいて描いた『西遊記=原題『ぼくのそんごくう』=の表紙絵二点を始め、二冊同時刊行予定だった二か月分の原稿を、手塚先生の自宅にお返しに上がりました。
この時の僕は、光文社から給料をもらっている、当然光文社側の人間ですから、「社長の独断で発行契約を破棄して申し訳ありません」とお詫びするつもりで行ったのですが、顔を合わせるなり手塚先生に、「野口さんすみません。でも、ボクのせいじゃありませんから」と、おっしゃられてしまい、どぎまぎしてしまいました。
「当然です。全面的に光文社側の責任なんです」と言ったきり、後は会話が続きません。帰ろうとして、馴れ親しんだ手塚邸の仕事部屋を出ようとした僕に、手塚先生が、別れの言葉を投げかけてくださいました。なんと、
「野口さん、漫画を描いてください」
と、おっしゃったのです。
そりゃ無理です。僕は編集屋で、漫画家じゃありません。と、言いたかったけれど、あまりの意外さに声にならず、回れ右して黙礼し、仕事部屋を出たのでした。
実はその後も、大都社に世話になっていた時、小学館では出しそうにない『ビッグコミック』連載終了直後の『奇子』を、大都社から出させていただいたり、(お願いの電話をかけた際、「出してもらえますか。ぜひお願いします」と、二つ返事でした)飯能に帰ってタネ屋を継いでからは、最後のご奉公と『鉄腕アトム』の銅像を造らせていただいたりと、手塚先生とのおつき合いは思い出したようにあったのですが、光文社の一員としてのお別れの際の「漫画を描いてください」の一言が、僕にとっては今でも、手塚先生が僕に託された遺言のような気がしてしかたありません。
今朝見た夢の話から始まって、思い出話を織りまぜたこの文章も、ずいぶん長くなってしまいました。
最後に、今朝の夢について、少し感慨にふけってみます。
今度、いつまた手塚先生と出会える夢を見ることができるのか、今はまったくわかりませんが、これまでもそうだったように、その時は、今朝の夢の続きのようなものを、見ることになる。と、思います。その時、手塚治虫先生が、夢の中でどんな絵を描いてくださるか(もう描いてくださると独り決めしています)、とても楽しみにしています。黄泉の国の手塚先生に、宿題を与えたような、けっこういい気分です。(笑)
逆に、先生から現し世の僕に与えられた宿題は、「漫画を描くこと」なのですが、中学生でその才能と、根気が続かないことに気付いた僕は、これを拒否します。その代り、現行版『火の鳥』の初代担当編集者として、また、手塚漫画の伴走者であり、変わらぬ愛読者の一人として、手塚治虫が一生かけて訴え続けた永遠のテーマ、生命の尊厳と地球の永続性持続のために、タネ屋の立場から志を引き継ぎ、表現していきたいと思います。
具体的には、今書かなくてはならない本を、『火の鳥・タネ屋編』または『火の鳥・野菜編』という視点で捉え直します。
(創森社の相場社長から、せっかく出版のお話があったというのに、また、わざわざ何度も飯能までお出ましいただき、内容についていろいろ案を提示していただいて、レジュメを詰めていく作業を重ねるうちに、なんだか自分の本とも思えなくなり、最近では、だんだんやる気を失ってきていたところでした)
今度は、来年の発行予定などに縛られることなく、手塚先生にとって『火の鳥』が完結することのないライフワークだったように、僕が『火の鳥』を引き継ぐつもりで、経済社会が生み出した生命のオバケ、一代雑種や遺伝子組み換えの野菜たちがやがてたどり着く未来を考え、生命本来の有りようを、考え抜いてみたい。そんな、自分には不遜きわまりないけれど、手塚先生だったら必ず「そうこなくっちゃ」と、笑っていただけるような本に、じっくり挑戦したいと思います。
たぶんそれこそ夢の中でお会いした先生が、僕に託した夢だ。と、今日の今なら信じられますので。
ついでに言っておくと、手塚先生は、今、黄泉の国で、また漫画を描きたくなっているのではないでしょうか?そして、アシスタント候補の若者たちを集めているのではないでしょうか?
もしかすると、あの古ぼけた木造家屋に集まった若者たちは、若き日の小野寺章太郎や、永島眞一、藤本弘、矢野高行、吉村睦夫君たちではなかったでしょうか?
天国か地獄か極楽浄土か知らないけれど、(どうも夢の中の風景は、それらのどこでもないようなので)やがて黄泉の国の手塚治虫先生のそばに召された時、恥ずかしくないような手塚ファンだった証しを、なんとか残して置きたい。と、今朝の夢からまだ覚めていない、今日の、今現在、考えているところです。
(2006/12/8)
【MEMO】
・・・と、言うわけで、2007年1月1日から、少しずつ書き始めることにしました。
無理矢理新しいことも考えられないので、内容は最近の講演の焼き直しですが・・・
〒357-0038 埼玉県飯能市仲町8-16 野口のタネ/野口種苗研究所 野口 勲
Tel.042-972-2478 Fax.042-972-7701 E-mail:tanet@noguchiseed.com
タネの話あれこれTOP 野口種苗目次